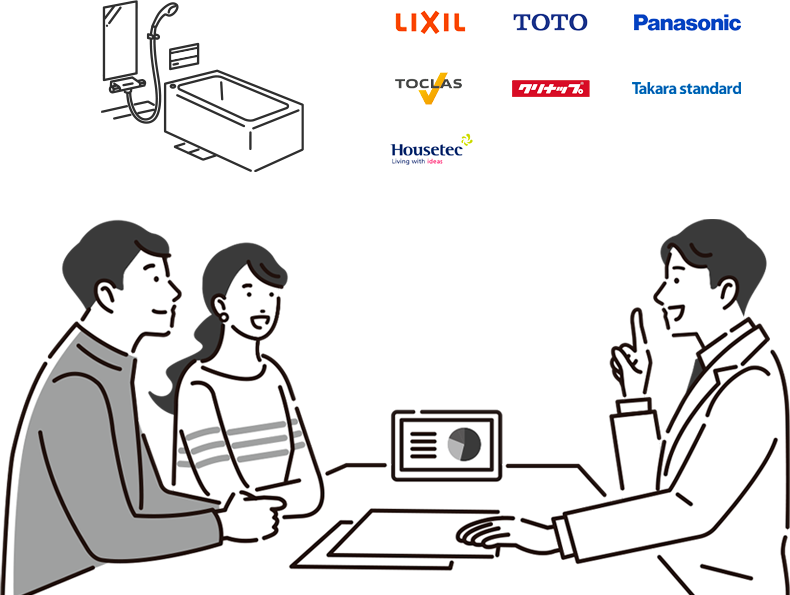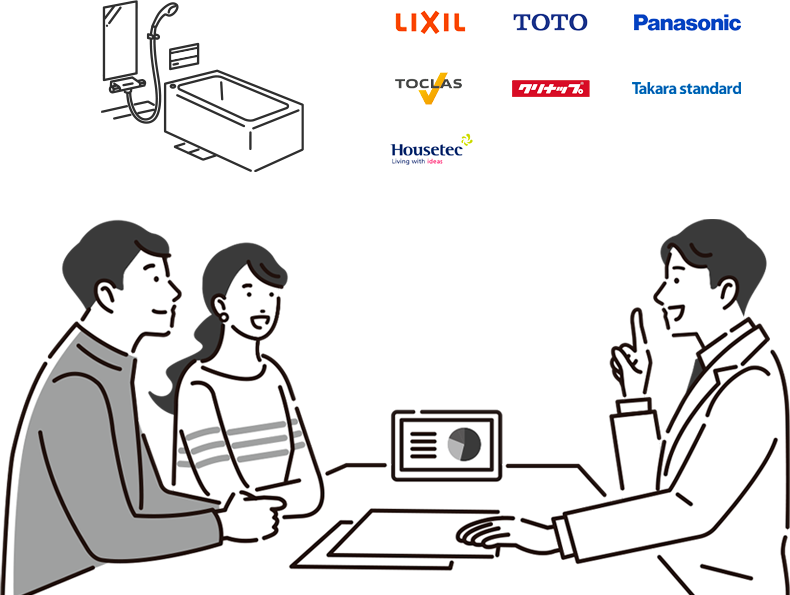投稿日:2025年5月9日| 最終更新日:2025年5月11日

高齢の家族がいるご家庭では、「お風呂での転倒が心配」「介助しづらい浴室をどうにかしたい」と感じていませんか。
実は、浴室をほんの少し工夫するだけで、日々の入浴が驚くほど安全でラクになります。
本記事では、介護を意識したお風呂リフォームで押さえておきたい7つのポイントを、具体的な設備やレイアウト例を交えて分かりやすく解説します。
この記事を読むことでわかること:
ご家族もご本人も安心できる入浴空間をつくるために、まずはリフォームで見直すべきポイントを一緒に確認していきましょう。

高齢になると、足腰の筋力が低下し、ちょっとした段差や濡れた床でも転倒しやすくなります。
浴室は特に事故が起きやすい場所の一つであり、転倒やヒートショックといったリスクが日常的に潜んでいます。
今のうちからお風呂を「安全で使いやすい空間」に整えることは、ご本人の安心だけでなく、ご家族の介助負担を軽くすることにもつながります。
在宅介護の選択肢が広がる今だからこそ、早めの備えが大切です。

厚生労働省のデータによると、家庭内で起きる事故の中でも浴室は転倒や溺水のリスクが特に高い場所とされています。
段差や滑りやすい床、寒暖差によるヒートショックなど、高齢者にとっては見過ごせない要因が揃っています。
浴室事故は年間1万人以上が命を落とすとも言われており、予防のためのリフォームは重要な対策の一つといえます。
バリアフリー化の実践ポイントは、こちらの記事でも詳しく紹介しています。

高齢者の入浴は、「またぎにくい浴槽」や「滑りやすい床材」が負担になりがちです。
また、介助する側にとっても、動きにくいレイアウトや出入口の狭さは大きなストレスになります。
在宅介護を見据えたお風呂のリフォームでは、本人の動きやすさだけでなく、介助する人のしやすさも考慮した設計が求められます。
ご本人とご家族双方の安心と負担軽減を目指すなら、今のうちから設備や動線を見直しておくことが将来的な安心につながります。

お風呂の介護リフォームを成功させるには、ただ「安全そうな設備を選ぶ」だけでは不十分です。
使う人の動作や介助者の負担まで考慮して、細かな設計や設備選びを行うことがポイントになります。
ここでは、実際にリフォームを検討する際に押さえておきたい7つの視点について、それぞれわかりやすく解説していきます。

浴槽の高さが高すぎると、またぐ際にバランスを崩して転倒する危険があります。
最近では、低床型の浴槽やフラットライン浴槽など、またぎ高さを40cm以下に抑えた商品も増えてきました。
足を大きく上げずに浴槽へ入れる設計にすることで、入浴への不安が和らぎます。
浴槽の形状や素材にもこだわることで、さらに安全性が高まります。
昔ながらの浴室では、脱衣所との間に5〜10cmほどの段差があることも少なくありません。
小さな段差でも高齢者にとってはつまずきやすい要因になります。
浴室と脱衣所の床をフラットに揃えることで、車椅子や歩行補助具を使う場合にもスムーズに出入りできます。
施工には床の高さ調整や排水処理の工夫が必要になるため、事前の確認が大切です。

浴室の床は常に濡れている状態のため、素材によっては非常に滑りやすくなります。
介護リフォームでは、滑りにくさと乾きやすさを両立した床材を選ぶことが重要です。
転倒事故の予防だけでなく、掃除のしやすさや足ざわりの快適さも考慮して選ぶと、毎日の入浴がより安心なものになります。

手すりは「あるだけ」では十分とは言えず、使う人の動線に合った位置に設置することが重要です。
浴槽の出入りや立ち座り、シャワー時の体勢保持など、動作に応じた配置が求められます。
L字型や縦型などの組み合わせで、複数箇所に設置するのが一般的です。
施工前に実際の動きをシミュレーションしておくと失敗しにくくなります。
開き戸は、ドアの開閉スペースが必要なうえに、倒れたときに外から開けられないという問題があります。
介護を意識した浴室では、引き戸または外開きの折れ戸がおすすめです。
引き戸なら車椅子でも出入りしやすく、浴室前の動線も広く確保できます。
幅も65cm以上を目安にしておくと、将来的な使い勝手にも対応できます。
浴室内が狭すぎると、介助者の動きが制限されてしまい、安全なサポートができなくなります。
入浴動作に必要なスペースを確保することは、被介助者・介助者の両方にとって重要な配慮です。
動線の確保や浴槽と洗い場の位置関係を見直すことで、介助のしやすさが大きく変わります。
必要に応じてレイアウトの変更も検討しましょう。

急激な温度差によるヒートショックは、高齢者の入浴時に多く発生しています。
特に冬場の浴室が寒いと、血圧が急変し意識を失う危険もあります。
壁や床、天井に断熱材を入れるほか、浴室暖房乾燥機を設置することで温度差を抑えることができます。
断熱浴槽との併用で、入浴前後の冷えも予防できます。

高齢者の安全な生活を支えるために、介護リフォームは重要な選択肢となります。
費用や補助金の情報を正しく把握し、計画的に進めることが大切です。
以下では、工事内容別の費用目安や利用可能な補助金制度、申請の流れについて詳しく解説します。

介護リフォームの費用は、工事の内容や範囲によって異なります。以下に代表的な工事とその費用目安を示します。
| 工事内容 | 費用目安 |
|---|---|
| 手すりの設置 | 約5万~15万円 |
| 段差の解消(スロープ設置等) | 約2万~45万円 |
| 滑りにくい床材への変更 | 約3千円/㎡~ |
| 引き戸への扉の取替え | 約10万~15万円 |
| 腰掛付きの浴槽への変更 | 約8万~10万円 |

介護リフォームには、国の介護保険制度や自治体の助成金制度を活用することで、費用負担を軽減できます。
介護保険制度では、要支援または要介護の認定を受けた方が対象となり、住宅改修費用の9割(上限18万円)が支給されます。
支給限度額の20万円は、数回に分けて利用することも可能です。
また、自治体の助成金制度もあり、介護保険の対象外となる工事や、要介護認定を受けていない方でも利用できる場合があります。
制度の内容や条件は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。

補助金を利用する際には、以下の点に注意し、適切な手続きを行うことが重要です。
申請の流れは以下の通りです。
補助金制度を活用することで、介護リフォームの費用負担を軽減できます。
制度の詳細や申請方法については、お住まいの自治体にお問い合わせください。
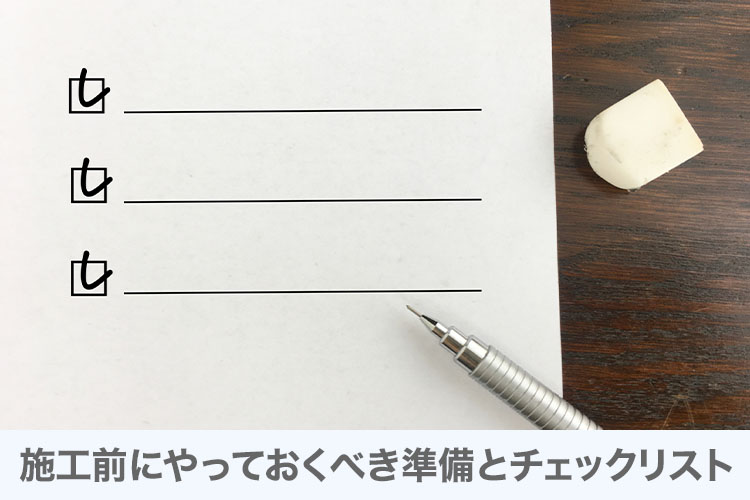
介護を見据えたお風呂リフォームを成功させるには、施工そのものだけでなく、その前段階の準備がとても重要です。
家族の希望や生活動線を明確にし、信頼できる業者を選ぶことで、納得のいくリフォームにつながります。
リフォームは、本人の身体状況や入浴スタイルに合わせた設計が基本です。
しかし実際には、家族の介助負担や使い勝手にも影響が出るため、双方の要望を整理しておく必要があります。
「何に困っているか」「どんな動作が不安か」など、実際の生活に即した視点で話し合いを行い、優先順位をつけておくと、後からの変更が少なくなります。
自宅の構造や本人の身体状況を踏まえた専門的なアドバイスを得るためには、介護の専門職の存在が欠かせません。
特に介護保険を利用する場合は、ケアマネジャーの意見書が必要になります。
福祉住環境コーディネーターは、住まいと介護の両方に配慮した具体的な提案ができるため、安心して相談できる存在です。
設計の初期段階から関わってもらうことで、使い勝手の良い浴室づくりが実現しやすくなります。
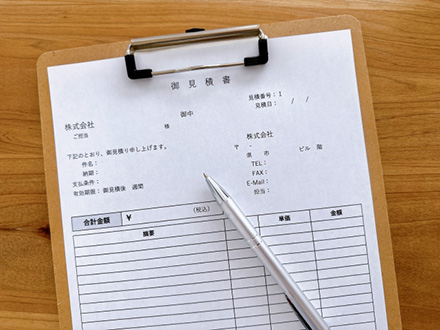
同じ内容のリフォームでも、業者によって金額や提案の質が異なります。
一社だけの見積もりで決めてしまうと、価格の相場がわからず、結果として高くついてしまう可能性があります。
最低でも2~3社から相見積もりを取り、工事内容やアフター対応の違いも比較することが大切です。
担当者の対応や説明の丁寧さも、業者選びの重要な判断材料になります。

実際に介護リフォームを行った家庭の事例は、検討中の方にとって非常に参考になります。
ビフォーアフターを見ることで、自宅にも応用できるヒントが得られるはずです。ここでは代表的な2つの成功例をご紹介します。

築25年の戸建て住宅にお住まいのご家族は、母親の転倒がきっかけで浴室のリフォームを決意しました。
以前は深めの在来浴槽で、またぐ動作が困難だったそうです。
工事では、またぎやすい低床型のユニットバスへ交換し、浴槽の縁には握りやすい手すりを設置。
入浴に対する不安がなくなり、ご本人だけでなくご家族にも安心感が広がったとのことです。
使う人の目線に立った設備選びが功を奏した好例です。
要介護2の父親と同居するご家庭では、介助者が一緒に浴室へ入る必要がありましたが、既存の開き戸では出入りに不便がありました。
また、床材も古く滑りやすいのが悩みでした。リフォームでは、浴室出入口を引き戸に変更し、床は乾きやすく滑りにくい素材に張り替え。
さらに、壁側の収納棚を撤去し、介助スペースを広く確保しました。
その結果、介助の動作がスムーズになり、入浴中の声かけや体の支えもしやすくなったそうです。
設備の変更だけでなく、レイアウトの見直しが快適性につながった好例です。

介護を必要とするご家族にとって、お風呂の時間は大きな負担となることもあります。
しかし、住まいの工夫次第で、その時間が安全で心地よいものへと変わっていきます。
本人だけでなく、介助する側の安心も得られる空間づくりが何より大切です。
安全性と使いやすさを両立したリフォームは、介護の負担を軽減し、家族みんなが心穏やかに暮らすための第一歩です。
設備の選び方やレイアウトの工夫、補助金の活用まで、できることから少しずつ進めていきましょう。
今回ご紹介したポイントを参考に、ご家庭に合ったお風呂づくりを進めていただければ幸いです。